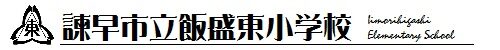算数科で計算する力はもちろん大切ですが、計算するだけでは問題を解決できないことがたくさんあります。「35人の子どもが長いす1脚に4人ずつすわります。みんながすわるには長いすが何脚いりますか。」という問題を式だけで解くと、次のようになります。35÷4=8あまり3、8+1=9、答え9脚 です。この問題で3年生は悩みました。35÷4=8あまり3 だということはみんながすぐに分かったのですが、あまりが出てきて、さてこれはどのようにすれば答えが出るのか…?と考えたのです。そこで、今日の学習のめあてを「あまりをどうするのかを考えて答えをもとめよう」としました。まずはみんなで図にかいて答えがどうなるのかを考えました。図にかいてみると、4人というまとまりになれなかった3人をどうすればよいのかが分かりました。そうだ!この3人をすわらせるために、長いすがもう1脚必要だ!そこで、先ほどの式に戻ります。答え(8あまり3)の8は長いすの数、3は子ども、だから長いす8脚にもう1つ長いすを加えて9脚になる。これを式にかくと、8+1=9となるのです。算数科では問題場面からイメージしたことを式に表す力が必要です。具体→抽象という頭の中での作業です。でも、今日の問題では、この式から問題場面に立ち返って考える、抽象→具体という思考も必要になります。大人では意識しなくてもできる思考ですが、子どもはどのように考えればよいのかという思考の流れを学んでいます。算数科だけでなく、全ての教科で、子どもたちはこの思考をじっくりとつくっていっています。さて、この時間、子どもたちが頭を抱えて一生懸命考えたり、友達と考えを交流したり、自分の意見をみんなに広げたりする場面がたくさん見られました。よく頑張っていると感心しました。研究授業ではありませんでしたが、他の先生方も参観し、自身の学びにしていました。
投稿者プロフィール
最新の投稿
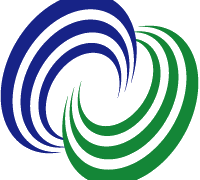 お知らせ2026年1月8日3学期 始業式
お知らせ2026年1月8日3学期 始業式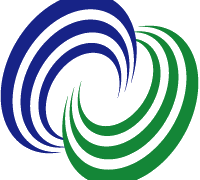 お知らせ2025年12月25日2学期 終業式
お知らせ2025年12月25日2学期 終業式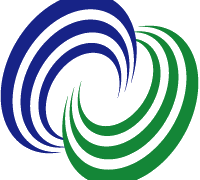 お知らせ2025年12月23日2学期最後の給食でした
お知らせ2025年12月23日2学期最後の給食でした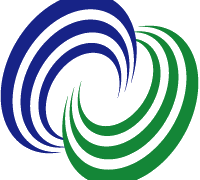 お知らせ2025年12月22日たくさん本を読んだで賞・6年生の読み聞かせ
お知らせ2025年12月22日たくさん本を読んだで賞・6年生の読み聞かせ